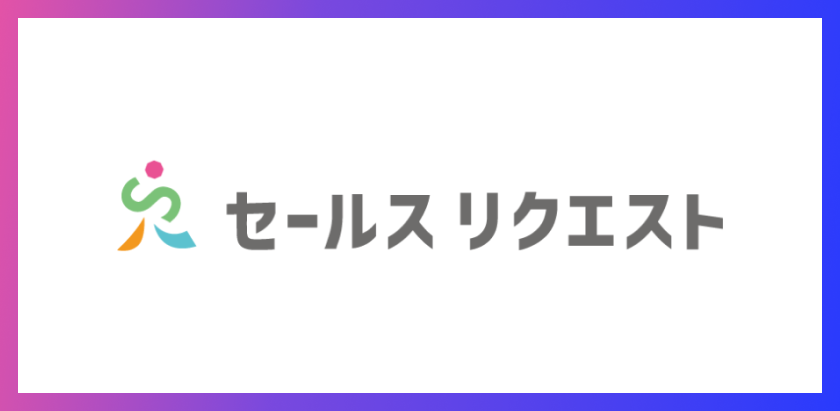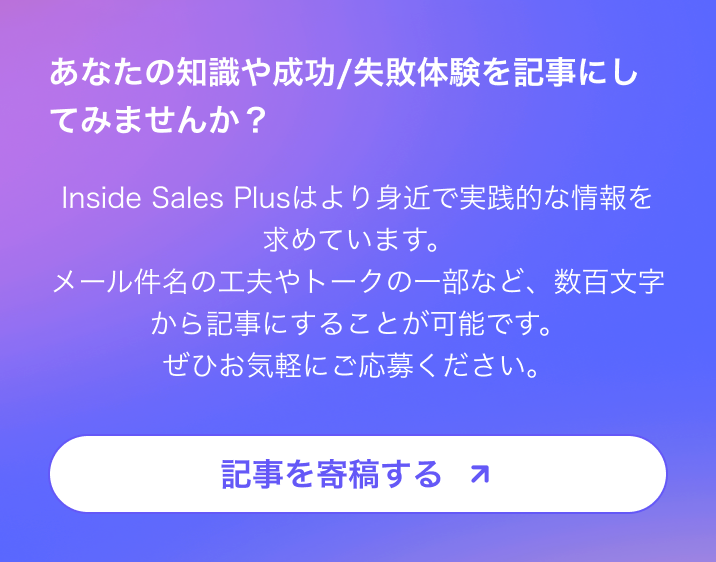はじめに──成果を「仕組み」で再現する、私の原点
現在、私はRevenue責任者として事業成長を牽引しています。その思想の原点は、キーエンスとAmazonという2社で培われた、再現性のある「仕組み」で成果を生み出す思想にあります。
新卒で入社したキーエンスでは、徹底した合理性の中で「データを基に成果を出す」ことの重要性を学びました。その後転職したAmazonでは、すべてのKPIが可視化されたECの世界で「成果は才能ではなく、仕組みで生み出せる」という確信を得ました。
この経験を武器に、SALESCOREでインサイドセールス(IS)組織の変革に取り組み、AIもフル活用し半年という短期間で目覚ましい成果を上げることができました。本稿では、その具体的なプロセスと実践知を余すことなくお伝えします。
半年間の成果──アポ獲得数5倍、アポ率は3倍以上に
私たちが最重要指標(KPI)として定めているのは、従業員400名以上の企業における「ターゲットアポ(APO)」の獲得数です。2024年12月頃、このターゲットアポは月間10〜15件でした。それが2025年6月には月間103件に到達。約半年で、アポ獲得数を5倍以上に引き上げることに成功しました。
また、見込み客と電話が繋がった後のアポ獲得率は、以前の10%前後から32〜40%へと3倍以上に向上。これは、会話の質やナレッジ共有、スクリプト設計といった「再現性のある仕組み」が成果に直結したことを示しています。
このブレイクスルーのきっかけは、一人のハイパフォーマーの存在でした。しかし、本質は個人の活躍ではありません。その「個の勝ち筋」を即座にチーム全体で模倣し、組織の「共有知」へと昇華させる文化と仕組みこそが、今回の変革の核となりました。
変革の背景──エンタープライズ市場という新たな壁
変革以前、私たちは中堅企業向け市場で順調に成長していました。しかし、事業戦略の転換により、より大きなインパクトを求めてエンタープライズ市場へ舵を切った瞬間、巨大な壁にぶつかります。
- 通電率の低下:ターゲット企業に電話すらつながらない。
- 会話の質の課題:役職者との高度な対話についていけない。
- 長期化する商談:大企業特有の複雑な意思決定プロセスに対応できない。
これまで機能していた仕組みが、全く通用しない。この理想と現実のギャップを埋めるため、「ISだけの努力では限界がある」という痛感のもと、組織横断での変革が始まりました。
課題の本質と、変革の意思決定
私たちが向き合った課題の本質は、「誰かの努力不足」ではなく「構造として成果が出にくい」という点にありました。ISチーム内ではスキルが属人化し、マーケティングやフィールドセールス(FS)との連携も噛み合っていませんでした。
最大の論点は、ISとFSの役割分担です。「質の高いアポ」にこだわりすぎるとISのアポ獲得数が伸びず、質を下げればFSの成約率が落ちる。このトレードオフに対し、私たちはあえて「ISのアポ獲得難易度を下げ、FSの初回商談の難易度を上げる」という意思決定を行いました。
これは、FSにコンサル出身者などの高スキル人材が多く、複雑な商談でも価値を提示できる体制が整っていたからです。この「どこで難易度を持つか」という組織全体での再設計が、変革のすべての起点となりました。
実行プロセス①:KPIを「行動のものさし」に変えた日次マネジメント
まずISチームが取り組んだのは、「目標はあるが、日々何をすべきかが見えない」状況の打破です。そのために、KPIをフルファネルで再定義し、目標を「日次×個人」までブレイクダウンしました。
【日次で回す高速PDCAサイクル】
- 朝会:その日の目標アポ数を宣言し、リードの質に基づいた架電計画を各自で立てる。
- 昼会:午前中の結果をチームで共有。「このリストの反応が良い」「このトークが響いた」といった情報をリアルタイムですり合わせ、午後の作戦を立て直す。
- 夕会:1日の結果をKPIベースで振り返り、良かった点・不足点を整理して翌日の行動計画に落とし込む。
これにより、KPIは単なる「管理指標」ではなく、日々の行動の拠り所となる「ものさし」として機能し始めました。
実行プロセス②:ハイパフォーマーの「暗黙知」を「共有知」へ変えたOJT
次に、新人ISの習熟曲線を急激に立ち上げるため、強度の高いOJTを導入しました。
新人ISがハイパフォーマー2名の間に座り、以下のサイクルを1日数十分、リアルタイムで繰り返します。
- ライブ通話を聴く:ハイパフォーマーの実際のトークと架電ペース(量)を肌で感じる。
- 新人の架電→即時FB:通話直後、「今の事例は効果的だった」「次はこう話そう」と数十秒でフィードバックを受ける。
- 思考の言語化:ハイパフォーマーが「なぜその順番で質問したか」を言語化し、思考プロセスを可視化する。
- 即時リトライ:FBを次の架電に即反映し、結果をまた共有する。
この仕組みにより、ハイパフォーマーの「暗黙知」が、誰もが使える「共有知」へと変換され、チーム全体のスキルが劇的に底上げされました。
実行プロセス③:マーケ・FSと部門の壁を越えた「全体最適」の連携
今回の変革の核心は、IS単体の改善ではなく、マーケティング・FSを含めた全体設計にあります。
マーケティングとの連携
施策カレンダーを共有し、リードの質と量を事前に把握。
リアルタイムな顧客行動(サイト閲覧など)があれば、5分以内にISが架電できる体制を構築しました。
(5分以内に架電できるようにTGT判定のロジックや5分以内に架電出来なかったリード数を可視化し、運用の強度を担保)
フィールドセールスとの連携
ISはターゲット条件(企業規模・役職)さえ満たせば、温度感が低い情報収集目的のアポも許容し、アポ獲得数を最大化しました。
FSは、温度感が低い商談でも価値を訴求できるよう商談資料を再設計し、初回商談のゴールを「課題の言語化」に設定。これにより、50%以上の案件化率を維持しました。
実行プロセス④:AIで作業を徹底的に自動化し、付加価値の高い業務に100%集中できる体制を実現
狙いは、架電に集中する時間の最大化と、誰が担当しても一定品質で再現できる標準化です。そのために、AIで「メールのたたき台作成」「SFA入力」を自動化し、人は架電の量と質の向上に専念できる状態をつくりました。
【AIで置き換えた作業と自動化の範囲】
メールのたたき台自動作成
通話内容・接点情報・自社事例を入力に、状況(不在/即切れ/日程未調整など)を自動判定し、件名・本文・行動喚起(CTA)をシチュエーション別に高精度でカスタマイズ。
※CTA=「次にしてほしいこと」を明確に伝える一文(日程候補から選ぶ/資料を見る/このメールに返信など)。
カレンダー連携で日程候補を自動挿入し、担当者はたたき台をもとに自身の考えや想いを伝えるための編集をしてメールを送信する。
→ 1通15〜20分の削減と、フォローの量・質の均一化を実現。
電話結果の自動入力
文字起こしから要点を抽出し、自由記述に加えて以下の選択項目を自動判定で入力
例:活動内容[問い合わせフォロー/掘り起こし/ウェビナーフォロー等]
TEL結果[不通/受付ブロック/アポ獲得等]
次回アクション種別
担当者役職、ニーズカテゴリ、優先度
次回予定日時、関連タグ、録音リンク、所要時間 など
→ 入力漏れを抑え、記録の粒度と整合性を標準化し人による入力のブレをゼロに。
これにより、通電後フォローの速度と徹底度が揃い、ISは架電・対話に集中できるようになりました。結果としてアポ獲得の母数と確度が底上げされました。
まとめ──「部分最適」を超えて組織を動かす
本稿で繰り返し触れたのは、単一部門の改善(部分最適)には限界があるという事実です。マーケ・IS・FSという一連のバリューチェーンを一度バラし、「どこで事業成長の難易度を持つか」を組織全体で再設計したからこそ、私たちは短期間で大きな成果を手にできました。
その推進力となったのが、以下の3つです。
- KPI を「管理指標」から「行動のものさし」へ昇華させた日次マネジメント
- 「暗黙知」を「共有知」に変え、即座に称賛・展開
- 部門間の壁を越え、全体最適をデザインする意思決定
営業組織は、優れた設計と、それを実行し続ける文化によって強くなります。部分最適を捨て、数字を羅針盤に行動を回し続けること。それが、半年で組織の未来を塗り替えた、私たちの最大の学びです。
セールスイネーブルメントを日本で実現する為に、まずは自分たちが日本で一番セールスイネーブルメントを体現出来ている組織になる必要があると思っています。
目の前の課題をクリアし、組織で成果を出すことが当たり前になれば、さらに大きな課題をみんなで解きに行くことが出来ます。
その繰り返しこそが、全員が課題を楽しみ、その先にある達成の喜びをみんなで分かち合う、本物のモメンタムを生むと信じています。
.png?fit=max&w=600&h=450)